現代において、文章の持つ役割は極めて重要です。
例えば会社では大きなプレゼンの企画書や、ちょっとした会議での資料。上司や部下、その他外部の人と行うメールなど、全て文章媒体によってやり取りがされます。
ビジネスがうまくいく、いかない、はこの文章の出来にかかっているといっても過言ではありません。
またプライベートにおいても、普段使っているLINEもそうだし、気晴らしにみるSNSの投稿もそう。そこでの文章の出来がコミュニケーションを円滑にしたり、たった一つの投稿が場合によって人生を変えることにもなります。
なのでできることなら文章は上手に書く必要がありますし、文章が下手だと多くの弊害が生じてしまう。あるいは人に迷惑をかけてしまう。そのような時代に突入してきているのです。
とりわけ収益が関わるビジネスの場では、自分の文章が下手だと今言ったように多くの人に迷惑をかけることにもなり、場合によっては批判を受けることにも繋がります。
かくいう私も文章が下手です。マジで苦手です。これまでに在籍した会社では毎回長いだったり、わからない、つまらない。といった指摘を多くもらいました。
 shu
shu単純に嫌になりました・・・。
時には何十時間とかけて作った会議資料を、その会議の直前でボツにさせられることもありました。当時は本当に悔しかったです。
それでもなんとか空いている時間を見つけて書籍を読んだり、毎日勉強するなどしてこれまでやってきました。
今回文章が下手でもなんとかビジネスの現場でも生きながらえてきた筆者が、文章の改善法についてお答えします。
今文章が下手で落ち込んでいるという人はぜひ本記事を参考にしてみてください。私自身も自戒の意味を込めて書いていきたいと思います。
文章が下手。そう思わせてしまう場面。イライラさせるきっかけ
現代において我々は、文章と接する機会が非常に多いです。
多くの人がこの文章を多く使っているし、そしてみています。
何をするのにもこの文章がやり取りの基本です。
なのでできることなら自分も文章を書く際は上手に書けたほうがいいです。
そこでうまく書けない人というのは間違いなく煙たがられますし、イライラされます。迷惑をかけてしまうからです。
文章が上手に書けないのはもはやマナー違反だと言われる時代がきているのです。
我々の普段の日常生活に、この文章の出来がどのように関係しているのかみてみましょう。
普段のLINEのやり取り
例えば今は誰かと連絡を取る際、そこで用いられるのがLINEです。
LINEは本当に便利です。自分の伝えたいことを瞬時に相手に届けることができます。
その文章が読まれたかどうかも確認でき、コミュニケーションツールとして非常に重宝します。
自分の伝えたいことをすぐに届けられる。またそれを相手が確認したかどうかもわかる。コミュニケーションを重ねていく上でこんなにも便利なツールはありません。
このLINEは、仲の良い友達や恋人、家族と行うのが基本ですが、場合によってはビジネスで取引先の人と行うこともあります。
このLINEの目的は円滑なコミュニケーションです。LINEを使っているユーザーもそれを期待しているはずです。
このLINEではあんなにも簡単にメッセージを送ることができるわけで、誰もがこのLINEを使えば迅速なコミュニケーションをとることが可能なのです。
LINEがあればすぐに連絡が取れる。こうした期待をみんな持っているんですね。
しかしそんな便利なLINEを使いつつ、毎回何をいっているかわからない人がいます。
そこでは円滑にコミュニケーションを図っていきたいというのに、意味不明な文章を送る。あるいは短文で済む内容を長文で送ってくる。
はっきり言って迷惑ですよね。イライラしてしまいます。
しかもプライベートの利用ならまだしも、ビジネスパーソンに対してもそのような文章を平気で送る人がいます。
円滑なコミュニケーションを目的としているLINEユーザーからすると、これはすごいストレスになってしまうんです。
LINEは今最も多くの人が使うコミュニケーションツールです。そこでは文章でのやり取りが基本です。周りの人に迷惑をかけないようにしっかりと書けなければいけません。
上司や部下、外部の人とのビジネスメールのやり取り
今はコミュニケーションツールとしては、LINEが多くの場面で使われております。
元々メールがありましたが、今はこのメールをプライベートで使うことはほとんどないでしょう。
しかし依然としてビジネスの場ではこの外部メールが多く使われております。
やはりこのメールもインターネットを通じて、多くの人と簡単にやり取りができるため便利です。昔はこのメールもなかったわけですから、そのことを考えるとやはり便利ですよね。メールは未だ多く使われるツールというわけです。
先方との予定の打ち合わせ、上司への報告、部下への指示、メルマガの配信。ビジネスメールはこういったときに用いられるわけですが、このメールがうまく書けないことがまずい事態であることは火を見るより明らかです。
特に先方とのやり取りの際は気をつけなければなりません。
例えば論理が破綻していて、意味がわからない文章を書いてしまうことで、先方をイライラさせるだけでなく、再度問い合わせの手間を生じさせてしまうことにも繋がります。さらにそのような状況に加え、誤字脱字が多かったりすると最終的に信用を失墜させることにも繋がってしまうのです。
ビジネスはシビアです。真剣な場です。ビジネスメールはそのビジネスの進捗を管理するものなのできちんと書けなければなりません。
またそのような背景があるわけなので、外部とのやりとりだけでなく、社内においても同様に気を配らなければなりません。
日常会話
実は日常会話においてもこの文章力が影響しているんです。
会話が我々人間にとってどれほど重要であるかは、もはやいうまでもないことですが、その会話の内容の是非を握っているのもこの文章力なのです。
会話にも種類があります。家族や友人とダラダラ話す会話もあれば、ビジネスで行う会話もあります。また行政機関や銀行、その他サービスの利用における、窓口の人と交わす会話などもあります。
しかし総じて「この人、何を言っているかわからない」と思われてしまうと、会話は成り立ちません。またそのような会話は相手をイラつかせてしまうだけです。
会話は対話であって、相手と親交を深めていく作業のことです。それは相手がいて初めて成り立つものです。そのためそこで話すことは相手に理解してもらえる内容になっていなければなりません。相手が理解できない会話というのは会話ではないのです。
会話も文章も同じで、それを聞いたり、読んだりするパートナーがいます。その内容は必ずパートナーが理解できる内容になっていなければなりません。
相手に自分の主張を「理解」してもらうためには、相手のわかる言葉で、状況を順序立てて説明する必要があります。またその順序というのも、自然な規則だったり、あるいは論理的で理にかなっている必要があるわけです。
つまりは会話も文章も論理的でなければならないということです。
会話や文章も、行う以上は最低条件として相手が理解できる内容にする必要があります。それをきちんと届けてあげる必要があるのです。
これが文章においても会話においても求められることです。義務です。
それが果たされていない内容、つまり理解できない会話や文章、論理が破綻している会話や文章というのは、本来あってはいけないんですね。
相手も貴重な時間をさき、会話をしたり、文章を読んだりしているわけです。誰も意味のわからない話など聞きたくないし、そんなことのために時間を使いたくはないのです。
しかし実際はそうした義務が果たされていない内容が非常に多いです。
最低でも理解できる内容にしてあげないと、ただただ時間の無駄になってしまうため、注意が必要です。
SNSの投稿
今はSNSの発展で、多くの人が自分の文章を発信できます。掲出の内容も基本自由です。
世の中に多くの文章が出回るようになりました。
しかしその内容はひどいものばかりです。
先ほどのべたように、論理が破綻していてそもそもの内容が理解できないものが多いし、何やら記号が散りばめられただけのものや、知人しか分かり得ない暗号めいたものもよく見かけたりします。
もちろん投稿の内容は自由でいいし、それがSNSの良さだったりするわけですが、あまりにもクオリティが低いように思うのです。
誤字脱字だけならまだしも、意味のわからないものが多く散見され、肝心の内容のほとんどはアンチのコメントだったり芸人の不倫ネタだったりするわけです。しかし何故か逆にインプレッションが多かったりもするわけです。
日本人、本当に大丈夫かとそう思っている人も多いのではないでしょうか?こんなものにみんな時間を費やしていて大丈夫か?と。
私はSNSを見ていると嫌な気持ちになるので見る回数を減らしました。そのくらい嫌な場所です。
SNSは便利ですが、誰もが自由に掲出できる場所とあって、さまざまな文章がそこでは散見されます。
文章を書く目的とは何でしょうか?
インプレッションの獲得を目的に他人の足を引っ張ったり、他人を落とし込んだりするのが文章の目的でしょうか?
SNSを見ているとそのような気持ちになるし、日本人特有のあの豊かな表現や、言い回しはもう死滅していってしまうのではないか、そのようなことも考えさせられます。
文章が下手だとダメな理由
ここまで現代における文章クオリティの必要性に関して述べてみましたが、ここでは今までのことを踏まえて、文章が下手だとダメな理由についてさらに深く考察したいと思います。
重複する箇所もありますが、大事なことなので一緒に振り返ってみましょう。
- お金の関わるビジネス、そこは真剣な場所。
- 今は誰もが文章を書けなければいけない時代。
- それを読む人がいるということ。下手な文章はその人の時間と労力を奪う
お金の関わるビジネス、そこは真剣な場所。
文章能力の是非が強く問われてしまうのは主にビジネスの場においてです。外部と行うメール、社内用企画案の作成、クライアントへのプレゼン進行、業務の進行タスクの管理、上司への業務報告、同じく部下への指示。
これら全て文章媒体でやり取りがなされます。
ざっと挙げただけでもこのような事柄がありますが、表に出てこない部分もたくさんあって、そこも含めると本当に多くの場所でこの文章のやりとりが存在しています。文章能力の出来がどれだけ大切かわかりますよね。
可能性として、文章能力のない人間は、会社への信頼をなくし、作業を遅らせる。あるいは間違った方向へ進めしてしまう。そういう危険性があるわけです。
そもそもなぜビジネスの場においてここまでシビアになる必要があるのかというと、そこは真剣な場所だからです。戦場だからです。そこはお金を稼ぐ場所で、人々の生活に関わっております。相手の人生を左右しかねない、あるいは自分の人生も左右しかねない場所だからです。
そこに文章の出来が直接的にそこに関係しているのであれば、ある程度上手に書けなければいけませんし、会話もうまく行われなければいけません。
にも関わらず、書けない人があまりにも多い。しかも学ぼうともしない。これではいけません。
特にビジネスの場においてはこの文章と真剣に向き合わなければいけません。上手く書けるようにならなければいけません。文章の出来が我々の命運を握っているのです。
今は誰もが文章を書けなければいけない時代。
現代に限らずいつの世も、文章は人間にとって最も身近な存在でした。
文章は自分の思いを他人に伝え、コミュニケーションを取るための手段で、元より豊かな人間生活を送るために必要な存在だったからです。
あるいは娯楽として、この書き物というのは古くから人間に親しまれてきました。
文章は生活そのものだったんですね。
今もそうです。文章が我々の日常生活に深く関わっています。生活を送るために必要なもの。いつの世も文章とはいわば我々のステータスの一部なんです。
文章力が欠けているというのは、人間として欠陥を抱えているといっても過言ではなく、うまく書けないことは人間生活が一向に整わないのではないか、そのように私は思います。
特に現代においては更にこの文章が生活に浸透してきております。今はSNSで自分の文章を世界中に発信できる時代だし、会社や学校でもデスク作業が増え、文章作業が増えました。誰もが嫌でも文章と深い関係を持たざるを得ない時代になってきてしまったのです。
そこでは上手く書けないとお金を稼げない、或いは学校の評価もあがらないといった時代になってきており、それはつまり文章が上手く書けないことは人生に支障をきたしてしまうということなんです。
文章と人は常に密接な存在です。今は昔以上にこの文章能力の是非が問われるようになってきており、そこでは誰もが上手に文章を書けなければいけない時代になってしまったのです。
それを読む人がいるということ。下手な文章はその人の時間と労力を奪う
文章を書くということは労力が入ります。時間も掛かるし頭も使います。大変な作業です。
なぜそこまで苦労して文章を書くのかというと、読者に届けるためです。
会社の上司や仲の良い友達、或いはあなたが既に何かしらのライター活動をしているのであれば、あなたの作品を楽しみにしてくれているファンなど。
このような人たちに自分の考えや思いを知って欲しいから書いているわけです。
仲の良い友人やファンであればあなたの文章がどんなにめちゃくちゃでも頑張って読んでくれるかもしれません。
しかしビジネスでは違います。基本的にあなたの文章は楽しみされていません。
皆さん時間が限られている中で、それでも時間を捻出し、そのビジネスメールや資料を読んでくれるわけです。
もしそこでの出来が悪かったり、何を言っているのかわからないような文章だったらどうでしょう?ましてやそれが社内全員に配信されたものだったら?それは多くの人の時間を無駄にしてしまうことになるわけです。
なので特にビジネスの場における文章は気をつけなければなりません。
また仮にどんなにあなたの作品を楽しみにしているファンであってもそのようなことを繰り返していけば、いずれ期待を裏切り、ひいてはあなたが不利益を被ることになるのです。
その文章には必ず読者がいます。そして文章は人の時間を奪います。書いた本人だけでなく、読者の時間も奪って成り立つものなのです。
最低でもその費やした時間に見合った見返りを差し出さなければなりません。
その読者がいるから我々は書くわけで、読者がいるから成り立つわけです。読者が分かりやすいように書く。それが結局は自分自身のためにもなります。
誰もが書き物を余儀なくされる時代。今は書かなければいけない時代です。書くことは避けられないのです。そしてその書くにおいてはできれば上手に書かなければいけない。
つまり今は誰もが上手に書けなければいけないのです。
文章が下手な人の特徴
今は誰もが文章を上手に書けなければいけない時代です。
そこでまず文章が下手な人の特徴とはどういったところにあるのかについて明らかにしたいと思います。
文章は誰においても常に発生している作業なので、今自分が書いている文章がそのような文章に該当していないか確認してみてください。
- 論理が破綻している、何をいっているのか、何が言いたいのかわからない
- 句読点が多い
- てにをはの間違いが多い
- 誤字脱字が多い
論理が破綻している、何をいっているのか、何が言いたいのかわからない
文章は自身の思いを他者に伝えるための道具です。そこでは書き手の思いを読者に伝えるのが目的です。
つまり書き手の意図を読者に伝えることが目的ですが、そのためにはそもそも行ったことを「理解」してもらわなければならないわけです。
それを読んだ読者が「何を言っているのかわからない、意味がわからない」このような気持ちを抱いたら文章は失敗です。
それだけでは絶対に避けなければなりません。なぜなら文章本来の目的を達することができず、ただただ双方の時間を無駄にしてしまうからです。
多少長くても意味がわかる文章なのであればまだマシです。また仮に誤字脱字が多い文章でもいいのです。
意味がわからない。これだけは避けなければなりません。文章においてこれほど厄介なものはありません。
そこでまず先ほども述べたように、人の理解というのは論理的構成で成り立っているということに注目してください。
つまり文章というのは論理的構成で書いていくことで、理解を得られるということです。
そもそも「理解」というのは人がそれを「事実」だと認識した瞬間のことです。論理が破綻しているというのはつまり事実と異なる点があるということです。事実と異なる点を述べているということです。
事実があって初めて次へバトンがわたり、読者もその道に沿って読み進めていける。これが正しい論理的文章です。
そしてまずはその論理的構成を持って読者を理解させ、自分の文章の土俵に立たせる。
これが文章においては求められるスタートなのです。論理的でない文章はもはや文章ではありません。決してあってはならなことです。なぜならそれは理解できないので、単なる時間の無駄だからです。
そのような文章は下手にも届かない最悪な状況です。
かの有名な芥川賞作家の丸谷才一さんは文章は論理的でなければならないと述べられております。
文章は論理的構成をしき、前後できちんと話がつながるようにする。その関係性を保ちながら筆者の意見を理解してもらうこと。これが前提です。
つまり理解してもらうことです。
また難しい表現もなるべく避け、意味がわからない文章にさせないということが肝心です。
句読点が多い
ここから本章筋の話し入っていきますが、句読点の多い文章は嫌われます。
先ほども述べましたが、文章の基本は論理的であることです。そこでは読者の理解を得るために一連の流れ、つまり多少長い姿をしていることが多いです。
この句読点はそんな流れに対し、目印をつける役割を持っていると考えてください。息継ぎポイントのような感覚です。
例えば長い川を泳いで渡ろうとした時、息継ぎをしなければ渡ることはできません。途中で溺れてしまいます。
文章も基本長い形をしておりますが、そこでは理解をしてもらわなければなりません。長い川を泳いでもらわなければいけないわけです。
そう考えると息継ぎポイントである、この句読点も必要不可欠な存在だということです。
一方でこの息継ぎポイントである句読点は、その一連の流れに対し、区切りをつけたり、突起物を与えてしまうもので、本来の流れを弱めていることにも気づかなければなりません。
適切な箇所で撃たれている句読点は読者の理解を助けますが、多すぎるとかえって邪魔になり、理解を妨げてしまうことにつながるのです。本来のスピードがあれば泳ぎ切れたものを、休憩箇所が多いがために泳ぎ切れなかったという事態にもなりかねないのです。
親切心でこの句読点を多用する人が多いですが、多いものはむしろ逆効果です。
特に文章を書くことに慣れていない人に見られがちな傾向ですが注意が必要です。
てにをはの間違いが多い
「てにをは」とは、「は」「を」「が」「も」「に」など、語句と他の語句の間に挿入されるもので、これを適切に設置することで前後の正しい関係性が見えてきます。
例えば「そのコピーは僕がやりました」という文章と「そのコピーは僕もやりました」という文章とでは、意味が異なります。
この「てにをは」は、少しでも使い方を間違えてしまうと意味を誤認させてしまうため、注意が必要ですが、些細なポイントとなるため気づきにくい分、よく見られがちなミスです。
文章は正しい理解をさせることで本来の役目を果たします。
些細なミスで誤認されたとあっては悔しいですよね。この「てにをは」も注意が必要です。
誤字脱字が多い
敢えて言うまでもないことですが、誤字脱字は本当に気をつけなければなりません。
仮にきちんと読めば理解ができる文章だっとしても、この誤字脱字が多いせいで投げ出される可能性があります。
読むことさえしてもらえないと言う最悪な結果になります。
また誤字脱字が多いというのは、注意力がないだったり、適当に書いているという風に捉えられる風習があります。
読む方からすれば、それって舐められているなと思ってしまうのです。
特にこれはビジネスシーンでは気をつけなければいけません。上司に報告書を提出する際もそうだし、クライアントとやりとりを行うシーンでもそうです。
誤字脱字は他人をイライラさせるだけでなく、信頼も失います。またそもそも読まれないといったケースを招くことにもつながり、最悪の場合その後のコミュニケーションにも支障が生まれる可能性にもつながるのです。
文章が下手な人が抱えている問題や原因
文章が下手だと思われる特徴としては以上のようなものがありました。
文章は誰もが書くものです。そしてその文章を読む人が必ずどこかにいるということを考えた時、誰もが文章をきちんと書く必要があります。日常的に自分の書く文章で誰かをいちいちイラつかせてしまったら、人生において非常に損なことです。
しかしそもそもなぜそのような文章になってしまうのか?例えばてにをはの間違いが多かったり、誤字脱字の多い文章になってしまうのか?ということです。
その原因については一概には言いきれない部分ではあるのですが、主にどういったことが関係しているのかについて考えてみたいと思います。
思考を整理できてない、論理的な思考ができない。
書くこと=考えることです。
書き手の脳内、これが形になったものが文章です。
つまり、仮に良い文章があったとして、その良い文章は良い思考から作られているということ。一方で悪い文章というのは悪い思考から作られているということです。
自分で言っておいてこの「悪い思考」というものの説明に困ってしまいますが、いわゆる思考がきちんと整理されていない状況。今から述べようとしていることを正確に言語化できていない状況がこれに当てはまると思っています。
そのせいで何をいっているのかわからない、読者が理解できない、理解しづらい悪文になってしまうのです。
文章は思考が形になったものです。
なのでこのような悪い思考、見切り発車の状態で書いてしまうのではなく、思考を整えた状態、しっかりとそのことを言語化できるまでに突き詰めた上で書くことが重要です。
そうするだけで安易な悪文は簡単に避けることができます。
またしっかり言語化できるということは、自分でもその状況を明確的に、あるいは段階的に捉えられているということでもあり、そこでの段階で論理的な構成になっている可能性も高いです。
文章は最低でも論理的構成にし、読者に理解させなければいけないものというのはすでに述べているところですが、良文に関しては、書き手によってきちんとこの言語化がされた上で書かれていると思って良いでしょう。
言語化はそういう意味でも大切です。
文章を書くために最も大切な前準備ですが、文章が下手な人はこれができない状態で書いてしまっています。
そこを事前に落ち着いて思考を整える。そして今あるモヤモヤを言語化し、論理的構成を心がける。このことを念頭においてみてください。
読書習慣がない
文章が下手な原因について、それは書き物の習慣が少なく、書くこととはどういうことなのか?ということがわからないからです。
どんなに文章が上手な人も初めから上手だったわけではありません。
例えば子供の頃は誰も初めから文章を書くことはできません。そこはきちんと先生に教えてもらったり、家で文献を読んだり、出された宿題をこなしたりして、書き物とはどういうものかを学ぶから書くことができるわけですよね。
そのような場で「文章の連なり」を知る。或いは「このようなことを言う時はこういう言い回しや型が必要だ」ということを学ぶ。
いわば文章に慣れ親しむ。文章の心臓を知る。文章の呼吸や色々な顔の側面を知る。文章の法則を知っていくわけです。
文章が上手な人はこうした法則を脳内にたくさん持っています。それは普段から親しめば親しむほど、こうした法則をたくさん持つことができます。親しんだ分だけその法則の量が増えていくのです。
そして何かを書くとき、その法則を引き出しから出すことができる。あるいは書いていて、異変に気づくことができる。本来の書き方に自然と上方修正できる。
文章が上手な人はこうしたことが自然にできるわけです。なので彼らが書く文章というのは読みやすく、間違いが少ないんですね。
文章が下手な人はおそらくこの読書習慣があまりないはずです。
読書習慣を身につけること。これが文章上達を招くために一番率先して行うべきことです。
読み手に対する配慮が足りない
書き物は読者がいて初めて成り立ちます。そこでは読者が理解できることが前提ですが、それだけでなく読みやすいように心がけなければなりません。
読みやすい文章に我々は無意識に親しみを覚えます。
自分の書物を多くの人に読んでもらいたい。あるいは特定の人に読んでもらいたい。こうした狙いを持って我々は書くわけですから、このことも書物を書く上で心がけなければいけないところです。
それでは読みやすいと感じる文章と、読みにくいと感じる文章。両者の決定的な違いはなんでしょうか?
私はそれは書き手による「配慮」があるかどうかだと思っています。
やっつけで書く。推敲しないで公開する。自分の書きたいように書く。
こうした文章は乱暴に感じられたり、論理が破綻していたり、誤字や脱字が多かったりするものです。
またおそらくそのような状態では、先ほどの思考の整理すらままならないはずです。
一方で、この言い回しは回りくどくないか?誤字や脱字はないか?意味が通じているか?このように考えながら書いたり、最後に推敲してから公開することで、間違いに気づくことができ、また柔和な形に仕上げることもでき、結果的に読みやすい文章に近づけることができます。
公開までのスピードはダウンしますが、その一手間が読者にとって確実にプラスになるのです。
読者に対するこうした配慮は、物書きをする上で欠かすことのできない作業です。特にそれを多くの人に届けたいと願い書かれているものであれば。
文章が上手な人はきちんとこの作業を行います。逆に文章が下手な人はこの配慮が足りていないのです。
文章が下手でもうまくなる日々のトレーニング
今は誰もが文章を書くことが日常的になっております。
誰しもが文章を書くことが義務的になっており、そこではその文章を読む読者が必ずいます。その際良い文章を書ければその人との関係がより密接になったり、会社の評価も上がることでしょう。
なので文章を上手く書けるようになりたいところです。私ももっと上手く書けるようになりたいと思っています。
最後にここでは、どうすればもっと文章を上手に書けるようになるか、私がこれまでに行ってきた内容も含めて、おすすめな手法をお伝えします。
文章力を上げるインプット
文章が上達するための方法はインプットとアウトプット、これを上質よく、そして多くこなすことです。
まずはインプットからですが、そもそも「インプット」とは何かしらの媒体から知識を蓄えるということです。
その際ただインプットすればいいというわけではありません。例えば漫画ばかり読んでいても文章はうまくなりません。
なるべくなら文章の書き方に関しての内容はもちろん、少し難解な言葉が多く使われている過去文学なども読むようにしましょう。
そこでは「書くとはどういうことか」という文章に関する基本的な学びに触れることができ、また一方で文学ということで、そこではさまざまな基本的な文章構成を学べるとともに、読者を引き込ませる文法や話の持っていき方など、テクニック面を学ぶことができるからです。
これらを率先して読むことで一気に文章能力を高めることができます。
まずは今あげたような内容を読むということですが、次に「実際の読み方」に関しても肝心です。
ただ単にそれらを読むのではなく、綴られている内容を頭の中でイメージしながら、想像しながら読むことが大切です。
というのも読みながらその情景をイメージすることで、そのイメージと言葉が結びつきやすくなるからです。
例えば何かを書くとき「こういったことを言いたい」というイメージさえあれば、そのイメージが先行し、またそのイメージに連想され、文章が書けるようになるといったことです。
今の読み方に関しては抽象的なアドバイスとなり恐縮ではありますが、なんとなくでもいいのでイメージしながらやってみてください。
アウトプット、ブログ、SNSなど
アウトプットも文章力を上げる上では重要です。
そもそも「書くこと」というのは今の自分の頭の中にあるイメージを形にしていく作業です。
そのイメージを形にしなければ書くことはできません。いかに頭の中のイメージを形にしていけるか?これが文章を書くうえで基本的な作業となります。
しかしここで問題がでできます。そのイメージを形にすることができないということです。
そこで今回のアウトプットが効いてきます。
書けないという状態はまだ漠然としている、明確化、あるいは言語化が到達できていない状態です。
それはつまり明確化、言語化が苦手だということです。
そこを何かしらの媒体に書くことで明確化や言語化を促進させることがこのアウトプットにおいては最大の狙いです。
というのも何かを書こうとした時点で、その思考が促進されます。つまりアウトプットを行っていると、その言語化しようという思考が鍛えられ、言語化が得意になるわけです。
だからアウトプットを行って欲しいんですね。言語化能力を鍛えるために。
しかも今はSNSやブログなどの便利な媒体が整っています。こうした媒体を用いて積極的にアウトプットしていくことで確実に文章力が鍛えられます。
日課のトレーニングにしてみてください。
文章とは川の流れという形を知る、その形を意識して毎回書く
書くことは何かと日常的です。
しょっちゅう行うものです。時には寝不足の時も、失恋した時も、どんな時でも書かなければいけないのがこの文章です。
しかし人間にはさまざまな事情があり、その時々の体調の変化もあります。コンディションに左右されてしまうのが性です。
そこでもなんとか書かなければいけないので辛いですよね。
私もコンディションによく左右されます。
いかなる時でもある程度のものを書けるようになりたいので、そこで自分なりの「バイブル」なるものをいつも携え、それを意識しながら書いております。
それは「文章は論理的でなければならない」という意識です。本記事でも要所においてお伝えしてきた内容となりますが、私は論理的な文章を常に心がけております。それだけで自然と読める文章にすることができます。
文章に正解はないと言われる中で、それでも私は読者がいての文章であるということは念頭においており、最低でも読者の方が理解できる文章を心がけるようにしています。
理解できない文章だけは書かないようにしているのです。それさえクリアできれば及第点は取れるでしょう。
これはそのための話です。
読んでいて理解できない文章、それはつまり論理が破綻している文章です。
しかしただ「文章は論理的でなければならない」という意識を持っていればそのような文章にすることができるのかと言われればそうではありません。
私はその意識を持ちながら、前後が必ず繋がるようにして書いております。
それは前の文は後ろの文のためにあるということです。前の文は後ろの文を読ませるためにあるということです。
その文を読まなければ次の文章がわからない。そういった関係を常に築いていけば自ずと論理的な文章になり、さらには読んでいて面白い文章、長文でも読める文章にしていけると思うのです。
いかに後ろの文章を読ませるか?前の文がそのための布石になっているか?ということです。
そのような文章にしていくにはある程度のテクニックが必要です。
例えば私は「それで?つまり?だから?そもそも?」といった問いを生じさせ、それを次文に提示させるような書き方を心がけております。
何にせよ、前後のつながり。結果的にこの形に持っていくこと。そのための意識を強く持つことです。
私は文章を書くときは常に「文章は論理的でなければならない」という意識を強く持っております。
トレーニングの話とは違いますが、文章を書くときはこうした自分なりのポリシーを持って書いていくと良いかもしれません。そうすればブレずにコンディションにも左右されずにいつでもあなたなりの文章が書けるはずです。
まとめ。文章が下手なのもその人の特徴。色々な人がいる。障害の可能性もある。多めに見てあげて
文章は誰にとっても日常的なものです。
誰もが日常的に書かなければいけないもので、読まなければいけないものです。
ビジネスではメールや企画書など文章媒体でのやり取りが主流ですし、プライベートにおいてもLINEやSNS投稿など、そこでも文章媒体が基本です。
我々の日常の充実度は文章の出来にかかっているのです。
しかしまだまだ文章を書くことが苦手な人が多いです。
文章が苦手だと相手に不快な思いをさせます。場合によってその人の時間を全て無駄にしてしまう場合もあります。
それで自分の価値が下がる。人から疎がられる。
この文章時代において、文章が下手なことは自分自身を生きづらくさせてしまうのです。
できることなら文章能力を身につけましょう。ある程度の文章を書けるようになれば確実に良い方向に向かっていけるはずです。
もちろん中にはどんなに苦労しても文章が上手くならない人もいます。私も何年もトレーニングを積み重ねてきておりますが、いまだにこんなにも読みにくい文章を書いております。
また中には病気や障害を持った人もいます。
そこは無理なく、自分のペースでやっていけばいいのです。
文章能力は今は最も重要なスキルの1つに含まれます。
今日よりも明日。明日よりも明後日。少しずつ着実にスキルアップしていけば確実に我々の人生は豊かになります。
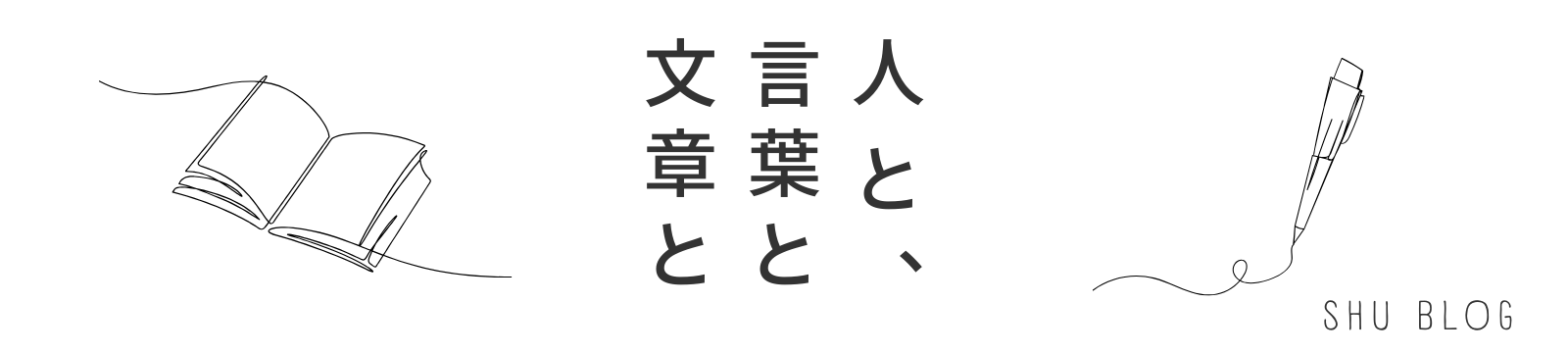

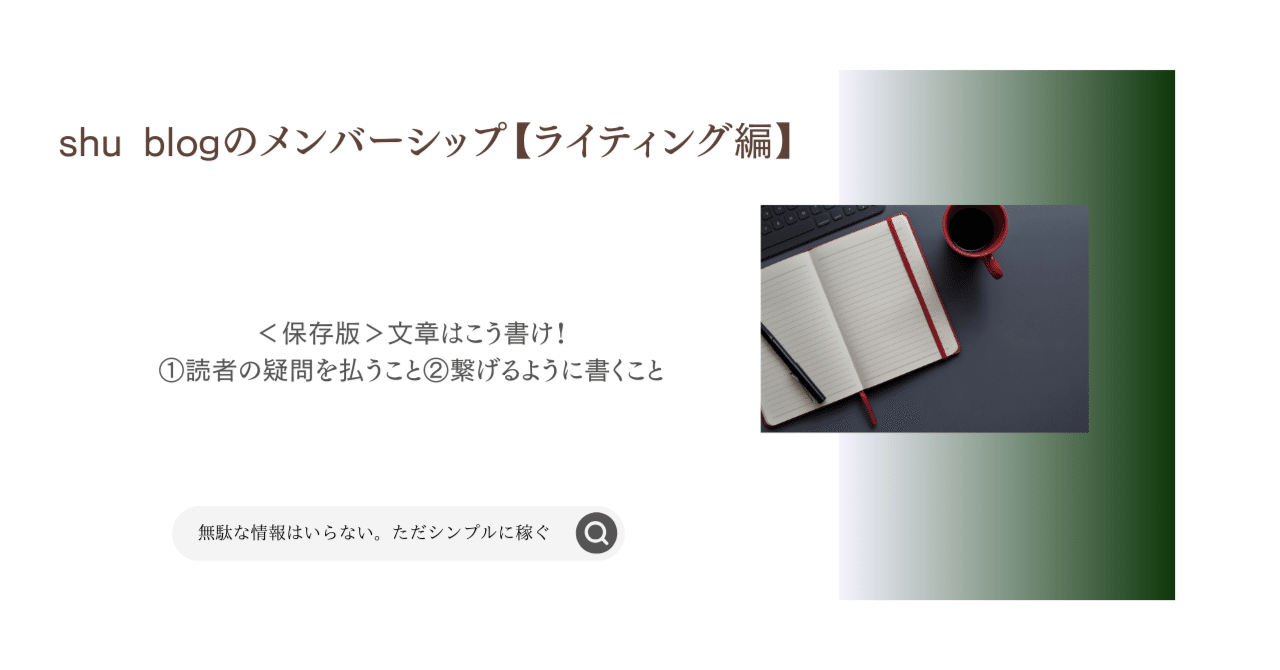


コメント